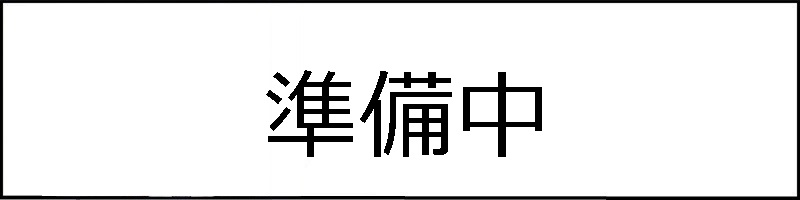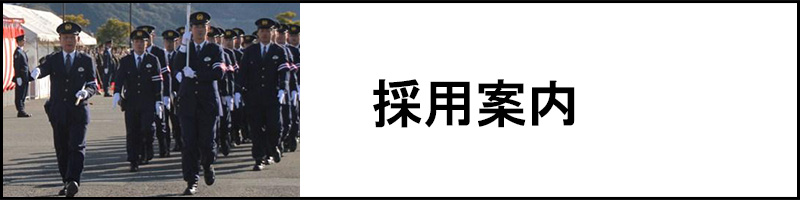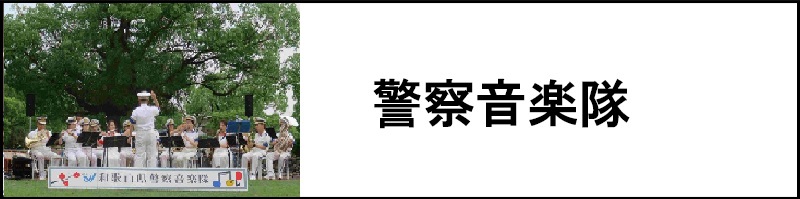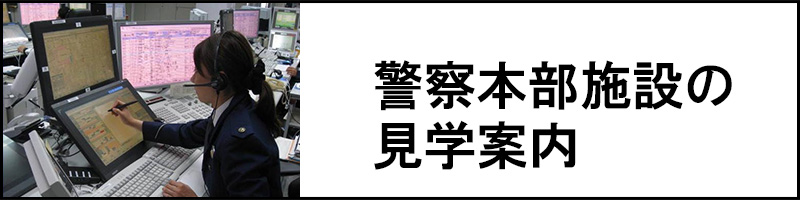家庭での災害への備え
南海トラフ巨大地震が発生すれば、県内で最大震度7の揺れと最大約20メートルの津波が襲来すると想定されています。
また、今後30年以内に大地震が起こる確率は、南海トラフ地震が80%程度とされています。
日頃の備え
- 家具類の配置を点検し、壁や柱などに固定する。
- 家具の上に重い物は置かない。
- ガラス製品(窓・家具)には、飛散防止フィルムを貼る。
- 避難場所は事前に決めておき、実際に安全に避難できるかを確かめる。
- 「家族防災会議」などで、災害時に落ち合う場所や連絡方法を決めておく。
- 非常持出袋(非常食、飲料水、懐中電灯、下着類、救急薬品、ラジオ、貴重品などを入れたもの)を玄関など、持ち出しやすいところに置いておく。

地震が起こったら
- 「グラッ」ときたら、屋内では机やテーブルの下などに隠れ、屋外ではブロック塀や看板等から離れる。
- 火の始末をする。
- テレビ・ラジオなどから正しい情報を入手して行動する。
- 津波・がけ崩れの危険地域からすぐ避難し、安全が確認されるまで戻らない。

津波からの避難の心得
- 地震が起きれば「津波てんでんこ」の教訓にならい、迷わず逃げる。「てんでんこ」とは、互いに家族のことを信じ、各自で高台に逃げることです。これはあらかじめ、家族などでお互いの行動を決めておき、離れ離れになった家族を捜したり、とっさの判断に迷って逃げ遅れたりしないようにすることが大切であることの教えです。
- 津波避難三原則の実践
「想定にとらわれるな」・「最善を尽くせ」・「率先避難者たれ」
- 津波は繰り返し襲ってくるので、警報・注意報が解除されるまで沿岸部には戻らない。
- 家具類の配置を点検し、壁や柱などに固定する。
- 家具の上に重い物は置かない。
- ガラス製品(窓・家具)には、飛散防止フィルムを貼る。
- 避難場所は事前に決めておき、実際に安全に避難できるかを確かめる。
- 「家族防災会議」などで、災害時に落ち合う場所や連絡方法を決めておく。
- 非常持出袋(非常食、飲料水、懐中電灯、下着類、救急薬品、ラジオ、貴重品などを入れたもの)を玄関など、持ち出しやすいところに置いておく。

- 「グラッ」ときたら、屋内では机やテーブルの下などに隠れ、屋外ではブロック塀や看板等から離れる。
- 火の始末をする。
- テレビ・ラジオなどから正しい情報を入手して行動する。
- 津波・がけ崩れの危険地域からすぐ避難し、安全が確認されるまで戻らない。

「想定にとらわれるな」・「最善を尽くせ」・「率先避難者たれ」